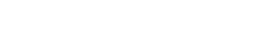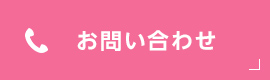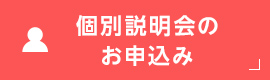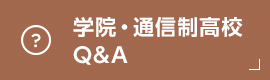2020/12/07
倭し麗し!晩秋の奈良大和路『長谷寺』
隠国の初瀬・古典読書会フィールドワーク
11月27日は秋の校外学習で初瀬の長谷寺を訪れました。先月始まった古典読書会のフィールドワークを兼ねての実施です。奈良県桜井市の長谷寺は686年(朱鳥元年)天武天皇の命により道明と言う僧が銅板法華説相図を安置したことが創始と伝わる名刹で『だだおし』と言う、旧暦正月の修二会で行われる追儺(鬼祓い)の儀式、火祭りで知られています。
また、長谷寺はおとぎ話『わらしべ長者』の舞台としても有名です。今は昔、正直者の貧しい若者が、長谷観音のお告げに従って手にしたわらしべを振り出しに、最後はその誠実な人柄を見込まれて、長者の娘と結ばれ、人々に徳を施すというお話です。わらしべ長者は若者のサクセスストーリーですから学院の生徒たちにも長谷観音様の霊験を期待しましょう。
今年の校外学習は京都御所や神戸中華街の南京町を考えていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で敢え無く断念、それならば地元の奈良大和路にも見どころはたくさんあるさ!と言う訳です。学院のある大和高田市からは近鉄電車大阪線で約20分の行程ですが、移動時間を短縮するため、各々自宅から最短ルートで現地『長谷寺駅』に集合です。
山の辺の道と優美な登廊・舞台造りの本堂
古くから門前町が発達した参道には、大きな杉玉が古き良き奈良大和路を感じさせてくれる造り酒屋や風情ある旅館、飲食店、土産物店などが軒を連ね、軽いハイキング気分で本堂を目指しますが、こんなに遠かったかな?足が重い!そう言えば、今年は外出自粛+テレワーク+移動は車=運動不足、健康に留意せよ!との観音様のありがたいお告げですね。
堂々たる仁王門をくぐると長谷型と呼ばれる楕円形の灯籠が吊るされた、下中上の三廊百八間、三九九段の優美な登廊(のぼりろう)を上り、本堂舞台で記念撮影です。観音信仰、物詣、舞台造り(懸け造り)と言えば、諺に曰く、清水の舞台から飛び降りる、京都の清水寺本堂が有名ですが、舞台からの眺望は奈良県民の贔屓目で見ると長谷寺が圧勝です。
全山燃えるような深紅の紅葉!と言いたいところですが、悲しいかな、少し早い時期に来ましたので紅葉はやや控えめです。その分観光客はちらほらでゆったりと拝観することが出来ました。古くは万葉集に詠まれた隠国(こもりく)の初瀬が駅のホームのような混雑では興醒めですと、強がってみますが、本音を言うとうらめしや新型コロナウイルスです。
険しい断崖に長い柱や貫で床下を固定し、その上に建物を建てる建築様式である舞台造りの外舞台からは、南に門前町がジオラマのように見渡せます。この眼下に望む初瀬街道を東へ進むと、名張や松阪を経て伊勢神宮、北に青垣の山裾を三輪から石上布留、春日へと続く山の辺の道、この地が仏教伝来の遥か以前から神聖な場所であったことが偲ばれます。
物詣と王朝文化『平安文学』の女性作家
本尊の寄木造り十一面観世音菩薩立像は、身の丈が三丈三尺(約10m)の巨大な立像で、戦国乱世只中の室町時代、1538年(天文7年)に仏師運宗らによって造立されました。長谷寺は度重なる火災で他の堂塔と同様、十一面観世音菩薩立像も実に七度も焼失しましたが、そのたびに再造を繰り返し、現在の本尊は八代目と言うことになります。本尊に対して左脇侍は雨宝童子立像、右脇侍は難陀龍王立像、それぞれ天照大神、春日明神に擬せられる、神仏習合の色濃い仏像群です。
十一面観世音菩薩のご利益は十種類の現世利益と四種類の来世の果報とされ、深い慈悲によって広く衆生を救う仏として知られています。医学や科学が進歩し、ウイルスによることが明らかな現代でもこの世上の混乱ぶりですので、当時の人々の観音信仰の深さは推して知るべしと思います。明治維新により苦境に陥った南都仏教界で、大寺院の内山永久寺が跡形もなく消滅し、長谷寺が往時のままであるのは、神仏が自然に融合し、広く大衆に支持されていたからだと考えられます。
今回の校外学習は先月始まった古典読書会のフィールドワークを兼ねていますので、源氏物語、玉鬘(たまかずら)ゆかりの二本の杉(ふたもとのすぎ)にも立ち寄りました。長谷寺には紫式部だけでなく、清少納言『枕草子』、菅原孝標女『更級日記』、藤原道綱母『蜻蛉日記』にも登場し、王朝文学全盛期の錚々たる女性作家が挙って訪れているので、彼女たちも参籠中に作品の構想や文章を練ったのかもしれません。清少納言は急坂だった当時の参道にかなりご立腹です。
今回のサプライズはよもぎの『くさ福餅』
さて、これも昭和の建立ながら、今ではしっくりと風景に溶け込んだ五重塔と落雷による火災によって明治時代に焼失した三重塔跡の見学が終わると、下りですので足取りも軽やかに帰路に就きます。ここで今回のサプライズイベントを発動、香ばしい焼き立ての名物『くさ福餅』をどうぞ。よもぎの香りと甘さ控えめのこし餡がベストマッチな逸品です。
奈良甘樫高等学院は通信制高校ですので、後期からの転入学生も多く、特に今回参加の女子たちはほとんどが初顔合わせとなりましたので表情が少し硬めです。そこで最終兵器の投入、スイーツ+女子=笑顔の方程式はやはり健在でした。
『二もとの杉のたちどを尋ねずはふる川のべに君を見ましや』
『初瀬川はやくの事は知らねどもけふのあふ瀬に身さへなかれぬ』
・紫式部『源氏物語』第二十二帖玉鬘より
追伸です『わらしべフィールドワーク』
初瀬詣と平安文学がテーマの奈良大和路・校外学習の写真は学校行事のフォトギャラリーにも掲載しました。コロナ禍により規模を大幅に縮小せざるを得ない状況下での実施ではありましたが、これは怪我の功名か、灯台下暗し、地元奈良県の歴史や文化財、自然の豊かさを再認識することができた、わらしべフィールドワークでもありました。長谷寺の東は天照大神が初めて降臨したとされる與喜天満神社、西は大物主大神の大神神社、最強のパワースポットを巡る旅でした。
相模の国、鎌倉にも本尊が同じ霊木から造られたと伝わる同名寺院がありますが、実は同じ社伝を持つお寺が学院のほど近く、大和高田市の南本町にもあり、長谷本寺(はせほんじ)と言います。今は小さなお堂ですが、盛時には古代の国道一号線、我が国最古の官道である横大路、竹内街道の大伽藍であったそうです。2024年の年末には長谷本寺を訪問、平安時代の御本尊や兜跋毘沙門天立像を礼拝し、役行者倚像や前鬼後鬼像も拝見して、ご住職に真言を唱えて頂きました。
しかし、返す返すも残念なのは『燃えるような深紅の紅葉』ですが、これをリベンジしたのが翌年2021年度の校外学習『錦秋の奈良紀行』山装う奈良大和路・夕映えの二月堂です。紀行文にまとめて、前年の太陽の塔・バーチャルスポーツ『過去と未来を旅する校外学習』とあわせてリンクを掲載いたしましたのでぜひご覧ください。最後に神仏が習合するパワースポット、桜井市初瀬の『長谷寺』と大和高田市の『長谷本寺』のホームページをリンクで紹介させて頂きます。
学校行事・学習活動リンク集
源氏物語の名場面二十二帖『玉鬘』二本の杉
2021年度の山装う奈良大和路紅葉リベンジ!
2019年度の万博・岡本太郎の芸術は爆発だ!
前回の奈良大和路フィールドワークはこちら
学院公式ブログ最新バージョンはこちらです
学院からのお知らせ・最新記事はこちらです
奈良県観光公式サイト・なら旅ネット山の辺
初瀬街道のパワースポット長谷寺公式サイト
竹内街道を守る観音様と毘沙門天の長谷本寺